飛鳥・奈良時代のはびきの
飛鳥時代になるとこれまで権力の象徴とされてきた前方後円墳が造られなくなり、小口山(こぐちやま)古墳や観音塚(かんのんづか)古墳のように内部に横口式石槨と呼ばれる特殊な構造の部屋をもつ小さな古墳が造られるようになります。さらに奈良時代に入ると 西浦古墓群のような火葬墓(かそうぼ)へと変化していきます。
一方仏教の伝来に伴って壮大な伽藍(がらん)をもつ野中寺(やちゅうじ)や西琳寺(さいりんじ)などの寺院が地域の豪族によって建設されます。集落の様相も竪穴住居から掘立柱建物へと変化して行きました。
市内では、古市遺跡などで竪穴住居が発見されていますが、その数は少ないと言えます。それに比べて掘立柱建物は、東阪田遺跡や車地(くるまじ)遺跡、伊賀遺跡などで数多く発見されており、この時期に急速に増加します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
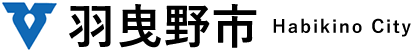


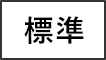
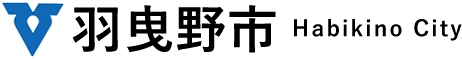
更新日:2024年01月19日