弥生時代とは
今から2,300 年ほど前、中国南部や朝鮮半島から稲作が伝わり、本格的な農耕が始まりました。木製の鍬(くわ)や 鋤(すき)、石製の斧(おの)石包丁などの農具も普及し、広い水田に用水路が引かれ、安定した食料の生産がおこなわれました。
大陸との行き来も活発で、青銅や鉄などの金属で作られた道具の生産がはじまり、剣や矢じりなどの武器、斧や鎌(かま)などの農工具、銅鐸(どうたく)や銅矛(どうほこ)のようなまつりの道具が作られました。日常の生活では縄文土器に比べると文様が簡素で実用的な弥生土器が使われました。
多くの人々が住む大きなムラには、全体をまとめるリーダーも現れました。時にはムラとムラとが争うこともあり、しだいに力のある大きなムラ、大きな権力をもった実力者が成長していきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
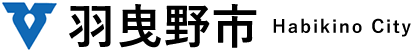


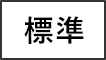
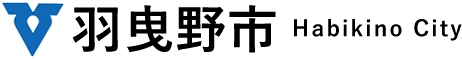
更新日:2024年01月19日