大阪府指定文化財
| 指定番号 | 名称・員数・時代・所有者・指定年月日 | 解説 |
|---|---|---|
| 建造物 第13号 | 西琳寺石造五輪塔 5基 (付)同跌石 1個 石造蔵骨容器 1口 (鎌倉時代・西琳寺) 昭和45年2月20日 | 昭和32年(1957)、工事中に高屋城跡の土塁の下からばらばらに埋められた状態で出土した。文安3年(1446)の「西琳寺流記」に見える「高屋宝生院」の叡尊、総持、道明寺開山の超運尼、浄意、空忍ら西琳寺に関係した高僧の供養塔とされる。いずれも花崗岩製で最も大きな叡尊塔とされるものは高さ3.1メートルあり、鎌倉時代の特色を備えた重厚なつくりである。 |
| 建造物 第23号 | 野中寺 僧房(そうぼう) 2棟 客殿 1棟 食堂(じきどう) 1棟 (江戸時代・野中寺) 昭和47年3月31日 | 野中寺は、聖徳太子建立の46院の一つで、「中の太子」とも呼ばれている。僧房は僧と尼が起居するところであり、客殿・食堂は大和郡山藩主の柳沢氏から寄進を受けた別邸を移築したものである。 |
| 彫刻 第40号 | 法泉寺木造聖観音立 像 1躯 (ほうせんじもくぞうしょうかんのんりゅうぞう) (平安時代 ・法泉寺) 昭和49年3月29日 | 明快な面相、重量感を感じさせる菩薩像で、大小の波を交互に配する衣文表現など、平安時代前期の作風が認められる。 |
| 工芸 第17号 | 法泉寺朱塗木造牡丹文猫脚型卓 (ほうせんじしゅうるしぬりもくぞうぼたんもんねこあしがたたく) 1基 (室町時代 ・法泉寺) 昭和49年3月29日 | 本尊をまつる須弥壇(しゅみだん)の前に置き、供養具を載せるための机である。牡丹の花の丸彫り、太い猫脚、朱漆塗りなど、宋の様式を取り入れた室町期の優れた工芸品である。 |
| 工芸 第19号 | 誉田八幡宮 太刀 銘 高井越前守信吉作(たかいえちぜんのかみよしのぶ) 1口 梨子地糸巻太刀拵付(なしじいとまきたちこしらえつき) (江戸時代 ・誉田八幡宮) 昭和50年3月31日 | 身幅の広い長大な姿に、互の目足の入った中直刃を焼く。信吉は京の五鍛冶の一人という初代信吉の子。山城・摂津・河内に3万石を領していた永井尚富が延宝5(1677)年に奉納した。 |
| 考古資料 第3号 | 徳楽山古墳石棺(とくらくやまこふんせっかん) 1基 (飛鳥時代 ・四天王寺大学) 昭和48年3月30日 | 徳楽山古墳は、羽曳野丘陵に存在した飛鳥時代の古墳で、墳丘が削平され凝灰岩で造られた横口式石槨が四天王寺大学構内に保存されている。 |
| 考古資料 第5号 | ヒチンジョ池西古墳石棺 1基 (飛鳥時代 ・野中寺) 昭和48年3月30日 | ヒチンジョ池西古墳は、羽曳野丘陵に位置した終末期古墳で、墳丘は消滅したが凝灰岩で作られた横口式石槨が野中寺境内に復元・保存されている。 |
| 考古資料 第23号 | 城山所在古墳出土 画文帯神獣鏡 (がもんたいしんじゅうきょう) 1面 太刀残欠(たちざんけつ) 1括 金銅飾履残欠(こんどうかざりくつざんけつ) 1括 琥珀玉(こはくたま) 1筒 (古墳時代 ・羽曳野市保管) 昭和56年6月1日 | 直径17センチメートルの画文帯神獣鏡の一部と鞘に綾杉文を刻んだ金の薄板を付けた大刀の一部、亀甲文を表す金銅製飾履の細片などで、明治時代前期に城山の八幡山古墳周辺にあった古市の旧家の土地から出土したもので、同古墳と関係する可能性もある。 |
| 考古資料 第60号 | 庭鳥塚古墳出土遺物 (古墳時代前期:羽曳野市) 平成28年4月5日 | 棺内からは三角縁神獣鏡、翡翠製勾玉、鉄刀、鉄剣が出土。三角縁神獣鏡は直径21センチメートルで銘帯を持つ舶載三角縁四神四獣鏡で古墳の築造年代よりも古い。棺外からは筒形銅器2、鉄刀3、鉄剣2、鉄槍3、鉄鏃135、銅鏃54鉄製篭手、鉄斧4、鉄鎌、鉄鋸が出土。武器武具類の出土が多いため、被葬者は武人的な性格の人物が浮かび上がる。 |
| 史跡 第41号 | 壷井八幡宮境内(つぼいはちまんぐうけいだい) 1件 (平安時代・壷井八幡宮) 昭和45年2月20日 | 寛仁4年(1020)源頼信は香呂峯に館を構え、河内源氏の本拠地とした。壷井八幡宮は前九年合戦の時、頼信の子、頼義とその子義家が戦勝を祈願した石清水八幡宮の神霊(八幡神)を康平7年(1064)勘請したことに始まる。現在、境内に建つ壷井八幡宮、壷井権現社は、元禄14年(1701)に徳川綱吉の命により柳沢吉保が普請奉行となって再建した。 |
| 史跡 第71号 | 庭鳥塚古墳 (古墳時代前期・個人所有) 平成28年4月5日 | 平成17年度に新規発見された古墳で、全長50メートルの前方後方墳で4世紀中頃に築造されたと考えられている。棺内からは三角縁神獣鏡をはじめとして筒形銅器や鉄刀など多くの副葬品が発見された。古市古墳群より少し前に築造された古墳で同古墳群を解明する上でも重要な古墳と考えられる。 |
| 天然記念物 第8号 | 壷井八幡宮のクス 1株 (壷井八幡宮) 昭和45年2月20日 | 高さ約30メートル、幹回りが約6メートルの巨大木です。江戸時代の享和元年(1801)に刊行された『河内名所図会』の境内図にも描かれ、「壷井の楠」として親しまれている。 |
| 天然記念物 第号 | 誉田八幡宮のエノキ (誉田八幡宮) 平成28年4月5日 | 樹高24メートル、幹回り3.3メートル枝張り東西18メートル、南北21メートルを測る。樹勢は旅行である。地表から高さ9メートルまで立て直し、そこで7本の支幹に分かれて斜めに広がり、直径18~21メートルの半球形の樹冠をつくりだしており、社叢の中でもひと際大きく、周囲の樹木より頭一つ飛び出している。樹皮もきれいな灰黒褐色で苔類の付着も少なく、100年を越える樹齢を感じさせない。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
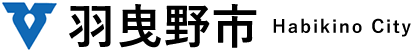


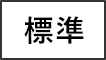
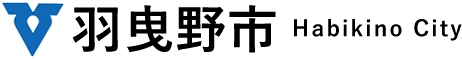
更新日:2024年01月19日