後期高齢者医療制度の給付
お医者さんにかかるとき
医療機関にかかったとき、療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(1割・2割・3割)を窓口で支払い、残りの額を後期高齢者医療から医療機関に支払います。
自己負担割合は、毎年8月にその年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)により定期判定を行います。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。
高額療養費

現役並み所得者2・1について
現役並み所得者2・1に該当する方でマイナ保険証をお持ちでない方は、申請により資格確認書へ限度区分を併記します。
なお、限度区分を併記のない資格確認書を提示した場合、「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用され、「現役並み所得者2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
低所得2・1について
低所得2・1に該当する方で、マイナ保険証をお持ちでない方は申請により資格確認書へ限度区分を併記します。
なお、限度区分の併記のない資格確認書を提示した場合、「一般:1割」の自己負担区分が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
|
低所得2 |
同一世帯の方全員が住民税非課税の方で、低所得1以外の方 |
| 低所得1 |
|
(注)下記の記載の食費・居住費については、高額療養費・払い戻しの対象外となりますので、事前に資格確認書へ限度区分を併記する申請をしてください。
入院時の食事代
入院されたとき、食費のうち標準負担額(所得区分・過去1年間の入院日数ごとに設定されています)を除いた額を後期高齢者医療が負担します。
| 所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食につきご負担いただく額) |
||
|---|---|---|---|
|
現役並み所得 一般 |
510円 | ||
| 指定難病患者 | 300円 | ||
| 低所得2(過去1年間の入院日数が90日以内) | 240円 | ||
| 低所得2(過去1年間の入院日数が90日超)(注2) | 190円(注3) | ||
| 低所得1 | 110円 | ||
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院していた方であって、引き続き医療機関に入院する方についても経過措置として260円となります。
(注2)低所得2と認定されてる期間の入院日数が対象となります。
(注3)適用を受けるためには保険年金課での申請が必要です。なお、金額の変更は、申請日の翌月からとなります。
申請に必要なもの
資格確認書等
入院日数が90日を超えていることが確認することができるもの(低所得IIで、過去1年間の入院日数が90日を超える場合)(領収書など)
療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食費と居住費を一部負担していただきます。
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
|
現役並み所得 一般 |
510円 (注1) |
370円 |
| 低所得2 | 240円 | |
| 低所得1 | 140円 | |
| 低所得1 (老齢福祉年金受給者) |
110円 | 0円 |
| 低所得1 (境界層該当者)(注2) |
110円 | 0円 |
(注1) 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。
それ以外の場合は450円(令和7年4月から470円)となります。
指定難病の方は300円となります。
(注2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者
療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
医療保険と介護保険の給付を受けたとき(高額介護合算療養費)
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を支給します。
支給対象となる被保険者の方には、3月上旬にお知らせ(支給申請書)を送付します。(送付時期が変更になっています。)
詳しくは下記ページを参照してください。
特定疾病
厚生労働省が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の療養を受ける場合の自己負担は月額1万円です。「特定疾病療養受療証」が必要になります。窓口に申請してください。
医療費の払い戻しを受けることができる場合(療養費)
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けることができます。
- やむを得ず資格確認書等を持たずに医療機関にかかったとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、一部負担金を支払うだけで済みます)
【参考】「整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方について」をご確認ください。 - 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請することができませんので、ご注意ください。
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと後期高齢者医療(広域連合)が認めた場合に限り移送費を支給します。
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割または2割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
交通事故にあったとき
「第三者行為による傷病届」の手続をしてください。第三者の行為によって傷病を受けたときでも後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療で医療費を一時立て替え、あとで加害者に請求します。
葬祭費
支給項目
葬祭費:5万円
どんなとき
被保険者が死亡したとき。葬祭を行った方に支給されます。
申請に必要なもの
- 領収書
- 喪主の方の振込み口座
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
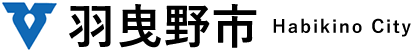


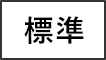
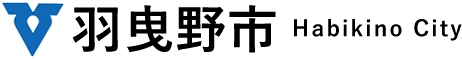
更新日:2025年10月01日