羽曳野市指定文化財
| 分類 | 名称・員数・時代・所有者・指定年月日 | 解説 |
|---|---|---|
| 工芸 | 座太鼓(ざだいこ) 1基 (室町時代・誉田八幡宮) 平成6年1月15日 | 舞楽に用いられた鼓で台付の座太鼓。ともに完全な姿で残り、太鼓の革にも三つ巴と宝相華唐草(ほうそうげからくさ)の美しい彩色が描かれている。技法に優れ、応永17年(1410)製作とある。 |
| 工芸 | 羯鼓胴(かっこどう) 1基 付.羯鼓台 1基(南北朝時代・誉田八幡宮)平成6年12月15日 | 舞楽に用いられた打楽器で、胴の部分に牡丹唐草文様(ぼたんからくさもんよう)が描かれている。切り口に墨書があり、正平6年(1351)に天王寺の怜人が奉公となって製作したことがわかる。 |
| 工芸 | 誉田八幡宮石造燈籠 (こんだはちまんぐうせきぞうとうろう) 1基 (江戸時代・誉田八幡宮) 平成10年2月10日 | 拝殿前に建つ四角型の花崗岩製石燈籠。請花、笠、中台部分は六角につくる。竿の銘には寛政18年(1641)に大橋龍慶の寄進であることが記されている。 |
| 工芸 | 壷井八幡宮石造燈籠 (つぼいはちまんぐうせきぞうとうろう) 1対 (江戸時代・壷井八幡宮) 平成12年3月31日 | 壷井八幡宮権現社の前にある、高さ2.92メートルの大型の石灯籠。花崗岩製の六角型で竿は円柱。壷井八幡宮再建を記念して、元禄14年(1701)に柳沢吉保が寄進した。 |
| 工芸 | 野中寺銅鐘(やちゅうじどうしょう) 1口 (江戸時代・野中寺) 平成18年3月31日 | 撞座には八葉複弁蓮華紋、2本の縦帯には天蓋と蓮華座上の月輪内に梵字が刻まれる。銘文により河州志紀郡太田村の桑野茂兵衛が、織田信長によって「天下一」の称号を与えられていた京都三條釜座の和田信濃大掾長寿につくらせ、寄進した。 |
| 絵画 | 阿弥陀浄土図(あみだじょうどず) 1幅 (鎌倉時代・大黒寺) 平成6年12月15日 | 画面の上半に極楽浄土、下半に阿弥陀と諸菩薩の来迎を描いた阿弥陀浄土図。金泥、銀泥、朱、緑青、群青など華麗に色を塗り分け、本格的な技法が駆使されている。 |
| 絵画 | 不動明王像 (ふどうみょうおうぞう) 1幅 (鎌倉時代・野中寺) 平成6年12月15日 | 右手に剣、左手に索(さく)を持ち、瑟瑟座(しつしつざ)に座す。岩の上にすわった不動明王像が描かれている。裏書には寛文3年(1663)、奈良西大寺の住職 高喜(こうき)から野中寺の中興恵猛(えんみょう)に授けられた。 |
| 絵画 | 伝僧形八幡神像 (でんそうぎょうはちまんしんぞう)1幅 (鎌倉時代 ・誉田八幡宮) 平成17年3月28日 | 錫杖と宝珠をもって雲上の踏み割り蓮華の上に立つ地蔵菩薩来迎の図様で表現されている。面長で端正な面貌、落ち着いた色調、截金と金泥で充填された文様などに、鎌倉時代後期の堅実な作風が残り、一流の仏師の手によるものと考えられる。 |
| 有形民俗文化財 | 藤花車 (ふじはなぐるま) 1台 (江戸時代・誉田八幡宮) 平成7年12月12日 | 三輪の上に井桁を組み、舞台をのせた古式のだんじり。舞台裏の墨書には、「藤花車」の名があり天和2年(1682)と文久2年(1862)に破損したため再造したとある。「河内名所図会」には旧暦4月8日の若宮の例祭で、華やかに飾られただんじりが笛や太鼓などの囃方をのせて曳行される様子が描かれている。 |
| 有形民俗文化財 | 藤花車飾布(ふじはなぐるまかざりぬの) 9点 (江戸時代・誉田八幡宮) 平成13年3月30日 | 河内木綿で作られた9枚の飾布。最大のものは縦287センチメートル、横444センチメートル。ベンガラや墨で型染めや筒描によって染色する。「河内名所図会」にも描かれており、数少ない河内木綿の実物である上に、大型で製作年代も明らかな貴重な例である。 |
| 古文書 | サク女日記 3冊 (江戸時代・羽曳野市) 平成7年12月12日 | 在郷町古市の商家の西谷家の長女サクが残した安政7年(1860)の日記。当時19歳のサクが父母にかわって店の経営や小作地の管理にあたったこと、近所や親せきとの付き合い、季節の行事、日々の出来事などが淡々と記されている。 |
| 古文書 | 市口家文書 9点 轡鍛冶連判証文 3通 苗字免許目打指示書 1通 轡注文書 1通 轡師御用控 2冊 牛馬渡世人詫状 1通 轡師御用礼 1通 (江戸時代・個人蔵) 平成14年3月30日 | 東高野街道沿いの誉田村鍛冶町で鍛冶屋を営んでいた市口左兵衛は、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いから敗走する薩摩藩の島津義弘(しまずよしひろ)の軍勢を住吉まで無事に案内した功績により、「薩摩藩御用轡師」になる。以後、将軍家にも献上され、「市口の轡」は全国に広がった。 |
| 古文書 | 吉村家文書 4点 嶋泉村検地帳(文禄3年) 1冊 嶋泉村検地帳(延宝6年) 2冊 嶋泉村田畠・屋敷絵図 1葉 嶋泉村領内絵図 1葉 (江戸時代・個人蔵) 平成15年3月31日 | 文禄の検地帳と田畠・屋敷絵図は一体をなし、領内絵図は延宝の検地前後の変化がわかるなど、太閤検地と江戸期の検地の貴重な史料です。 |
| 古文書 | 松倉家文書 1点 碓井村(うすいむら)人数帳 1冊 (江戸時代・個人蔵) 平成16年3月31日 | 寛永21年(1644)の年記をもつ、河内古市郡碓井村の人数帳で、村の人口、家族の名前・年齢・家の規模などが記されている。 |
| 史跡 | 薄田隼人正兼相(すすきだはやとのかみかねすけ)の墓 1件 (明治時代・羽曳野市) 平成8年11月12日 | 薄田隼人正兼相は、豊臣秀吉の馬廻り、秀頼の侍大将として活躍した武将で、慶長20年(1615)の大坂夏の陣(道明寺合戦)で道明寺・誉田の高台で討ち死にしたと言われている。 |
| 考古 | 西琳寺(さいりんじ)跡出土鴟尾(しび) 1体 (飛鳥時代・羽曳野市) 平成8年11月12日 | 鴟尾の全体がうかがえる稀少な例である。胴部と側面と鰭部には段違いの羽根状の模様を削り出し、腹部には火焔宝珠(かえんほうじゅ)と蓮華文(れんげもん)が浮彫りされており、仏教芸術の 新たな資料として注目される。 |
| 考古 | 小口山古墳(こぐちやまこふん) 1基 (飛鳥時代・羽曳野市) 平成19年3月30日 | 直径14メートルの円墳で、凝灰岩を刳り抜いた横口式石槨を設けている。石槨の周囲には安山岩を壁状に積み上げ、前面には羨道部を設ける。特異な形式の石槨として注目されている。 |
| 石造物 | 駒ケ谷の道標(神南辺隆光造立寄進) 1基 (江戸時代・駒ケ谷町会) 平成10年2月10日 | 金剛輪寺(駒ヶ谷)の学僧覚峰(かくほう)と面識のあった堺の鋳物師神南辺隆光(かんなべりゅうこう)が大峰山や金剛山への道しるべとして、竹内街道沿いに設けた。 |
| 歴史資料 | 阿闍梨覚峰関係資料 (あじゃりかくほうかんけいしりょう) 子(隼人)画像線刻石 1対 日谷稚宮銘石 1基 日谷稚宮祓禊之旧蹟銘石 1基 永手之墓銘石 1基 伝楠木正成塔 1基 伝清少納言塔 1基 付 清少納言塔献花石 1基 韴霊銘石 1基 韴霊銘石櫃 1合 付 藤原永手銘石 1基 付 伝楠木正成塔献花石 1基 (江戸時代・杜本神社) 平成22年9月1日 河内飛鳥川の歌碑 1基 当岐麻道越(たぎまじごえ)の歌碑 1基 (江戸時代:杜本神社・駒ヶ谷地区) 平成25年4月24日 | いずれも覚峰の歴史研究、顕彰の対象になった史実や文物の創作によって生まれたもので、人々の関心を地域に結び付けようとしたものと理解できる。なお、「永手之墓銘石」「伝楠木正成塔献花石」は、覚峰の遺志を継いだ神南辺隆光により造立されたものとされている。 また平成25年には、名所旧跡や社寺など探訪や参詣に大きく影響を与えた歌碑2基を新たに追加指定した。 |
| 建造物 | 誉田八幡宮の放生橋 1基 (江戸時代前期:誉田八幡宮) 平成27年12月18日 | 袖高欄と添束の様式から17世紀後半~18世紀前半頃に建造されたと考えられる。構造、意匠とも優れた近世石造橋の希少な作例で、建造当初の状態が良好に保存されている。各部の基本的な構造は伝統的な曲率の強い木造橋を模倣したもので、近世の石造橋の建造技術を示す典型的、かつ重要な作品と考えられる。 |
| 建造物 | 畑田家住宅 11棟 (明治時代、一部昭和時代:畑田耕一) 平成29年3月27日 | 江戸時代に村の重役をつとめた旧家の住宅。敷地の北東に主屋を置き、南東に長屋門とその西に2棟の土蔵が連なる。主屋の西には納屋、南には付属屋が建つ。座敷の間取りは田の字型で、土間の梁架高は古い伝統を残す。明治初期の旧家の屋敷構えや意匠をよく残している。 |
| 建造物 | 大津神社本殿 1棟 (江戸時代前期:大津神社)附 棟札11件(12枚) 平成31年4月19日 | 本殿は軒唐破風付き、杮葺の一間社春日造で、梁行7尺5寸、桁行7尺5寸、向拝の出5尺8寸の規模は春日造社殿の中では傑出した規模を持つ。建立年代は棟札により寛永17年(1640)であることが明らかで、建物の構造、意匠等の特徴もこれを裏付ける。棟札には、「摂州大坂住人鳥井長右衛門藤原朝臣正次」と同じく「作左衛藤原朝臣正吉」が大工であったことが判明。大工鳥井氏は「宮屋」の屋号と名乗り、江戸時代中期には数多くの社寺建築を造営し、その最初期とみられる当本殿は、鳥井氏が正統的な流れの中にある大工であったことを示している。なお、寛永17年から昭和63年(1988)までの棟札11件(12枚)は、本殿の建立と修理の年代や経過を伝える重要史料であることから、附・指定とする。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
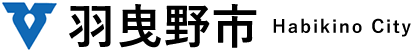


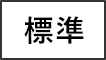
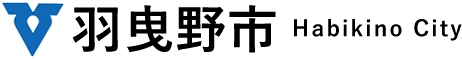
更新日:2024年01月19日