要介護認定について
概要・内容
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
この、要介護状態や要支援状態の判定、その度合いの判定を行うものが要介護認定です。
また、要介護(要支援)状態及び度合いの判定は、病気の重症度ではなく必要とされる介護の量で決まります。
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護認定ができる対象者について
| 第1号被保険者 | 65歳以上で介護や支援が必要になった方 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方 |
特定疾病などの詳細は、下記のリンクページをご覧ください。
申請から認定までの流れ
- 手続きに必要な書類(申請書)を羽曳野市高年介護課へ提出してください。
- 羽曳野市または市から委託を受けた認定調査員が心身の状況などについて調査を行います。
- 羽曳野市から主治医に心身の障害の原因である病気などの状況に関する意見書の作成を依頼します。
- 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家(介護認定審査会)が介護を必要とする度合いを審査・判定します。
- 介護認定審査会の審査・判定結果に基づき要介護(要支援)認定を行い、要介護認定結果等通知書と被保険者証を本人に郵送します。
詳細な流れについては、下記のリンクページをご覧ください。
要介護(要支援)の認定区分
要介護状態・要支援状態の区分は、次の7段階です。
| 状態区分 | 心身の状態のめやす(例) | 利用できるサービス |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要 | 予防給付における サービス |
| 要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状況の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態 | 予防給付における サービス |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要な状態であって、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態、または、認知症等により認知機能が低下している状態 | 介護給付における サービス |
| 要介護2 | 起き上がりが自力では困難なことがある。排泄・入浴などで一部または全介助が必要。 | 介護給付における サービス |
| 要介護3 | 起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。 | 介護給付における サービス |
| 要介護4 | 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になることが多い。 | 介護給付における サービス |
| 要介護5 | 日常生活全般にわたって介助なしでは生活できない状態。意思伝達も困難になる場合がある。 | 介護給付における サービス |
| 非該当 | 要介護状態にないと認定された場合 | 介護保険以外の 市のサービス |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536
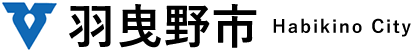


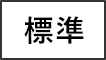
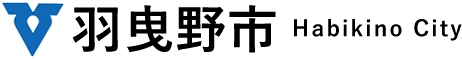
更新日:2024年08月27日