生産緑地地区について
生産緑地地区とは
- 市街化区域内(※1)の農地又は採草放牧地等(以下、「農地等」という。)であり、一団性を兼ね備える地区です。
- 農地等として30年(※2)の適正な管理が義務付けられ、それ以外の土地利用が制限されます。
- 固定資産税額が農地評価・農地課税となります。
(詳細は、税務課固定資産税担当にお問合せ下さい。) - 相続税の納税猶予制度を受けることができる要件となります。
(適用には他の要件も満たす必要があります。詳細は税務署にお問合せ下さい。)
※1:市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことです。ページ下部【生産緑地地区の指定状況】の各計画図で、オレンジの帯の内側が該当区域になります。
※2:指定されてから、30年を経過する生産緑地については、特定生産緑地に移行することができます。 詳しくは「特定生産緑地について」をご覧ください。
生産緑地地区の目的
生産緑地法の趣旨に照らし、市街化区域内の緑地機能(主に防災機能の向上やヒートアイランド現象の緩和等。)及び多目的保留地機能(主に公共施設等の敷地として適しているもの。)に優れた、農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的とします。
生産緑地地区の指定条件
- 市街化区域内の農地等であり、現に農業の用に供されていること
- 良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
※土地内外に垣または柵等を設ける必要がある場合は必要最小限とし、透視可能なものであること。外部から容易に出入りできること。などが必要です。 - 一団で300平方メートル以上の規模の区域であること
※本市では「羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、平成31年4月1日より生産緑地地区の面積要件を『500平方メートル以上』から『300平方メートル以上』に引き下げました。 - 耕作に必要な進入路や用排水路等、長期に亘っての農業の継続が可能な条件を備えていること
ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合は指定できません。
(1)指定の申出時に農地転用の届出等が行われている場合(農地法第4条・第5条。農地以外に利用する場合)(生産緑地法第8条において許容される施設(営農に必要な施設等)に転用される場合を除く。)
(2)生産緑地法第8条において許容されない施設(屋外広告物、売電が主目的の太陽光発電等)が立地する場合
(3)都市計画法第59条の規定による都市計画事業の認可又は承認が行われている場合
(4)原則として、過去に「故障に至った」ことで、法第10条の規定による買取りの申出を行う理由となった「主たる従事者」を、再度「主たる従事者」として指定の申出をする場合。
(5)コンクリートで覆う等により、雨水流出抑制の効果が乏しいもの。
生産緑地地区の管理等
生産緑地の管理
生産緑地地区内では、(特定生産緑地に指定するしないにかかわらず)農地等としての適正な管理が義務付けられます。
市や農業委員会が生産緑地の管理のために必要な助言、土地の交換の斡旋及びその他の援助を行います。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内では、(特定生産緑地に指定するしないにかかわらず)農地等以外としての土地利用(建築物の建築等)はできません。
※ ただし、必要と認められる施設については、許可できる場合があります。
生産緑地地区の買取申出
生産緑地地区内の農地等としての適正管理義務、 農地等以外としての土地利用(建築物の建築等)の制限について、制限を解除しようとする場合、以下の要件に該当したことをもって、下記の『買取申出の手続きの流れ』に沿って、手続きをする必要があります。
なお、要件を満たしただけで自動的に生産緑地地区における行為の制限が解除されるわけではありません。
買取申出が可能となる要件
- 指定から30年を経過したとき ※特定生産緑地に指定されていない場合に限る。
- 主たる従事者(※1)が死亡したとき
- 主たる従事者(※1)が農業に従事することを不可能にさせる故障(※2)の状態になったとき
ただし、2又は3に該当した場合であっても、主たる従事者を変更することにより、継続して営農することは可能です。
※ 土地所有者と主たる従事者が異なる場合、土地所有者の死亡・故障は、上記要件には該当しません。
| (※1)主たる従事者とは |
|---|
当該生産緑地における農業が客観的に不可能となるような場合における当該者をいう。
・農業に主に従事している者(生産緑地所有者や世帯主に限定されるものではありません。)
・従事者が複数人の場合にあっては、【主たる従事者が当該生産緑地に係る農業の業務に一年間に従事した日数】の八割以上従事している別の従事者を含む。(主たる従事者が65歳以上の場合においては、七割以上)
・都市農地貸借円滑法または特定農地貸付法に基づき貸借している場合、一割以上(契約等の基準あり)
| (※2)農業に従事することを不可能にさせる故障とは |
|---|
- 両眼の失明
- 精神の著しい障害
- 神経系統の機能の著しい障害
- 胸腹部臓器の機能の著しい障害
- 上肢もしくは下肢の全部もしくは一部の喪失またはその機能の著しい障害
- 両手の手指もしくは両足の足指の全部もしくは一部の喪失またはその機能の著しい障害
- a.からf.に掲げる障害に準ずる障害
- 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの
※ 故障の状態は、医師の診断書等の証明により、内容認否を判断します。
『高齢になった』『体力的につらくなった』などの自己申告の事由だけでは認定できません。
買取申出の手続きの流れ

| (※1)事前協議について |
|---|
買取申出には、事前協議が必要です。担当課までご相談ください。
なお、代理人の方での事前協議は可能ですが、委任状・本人確認書類が必要です。ただし、円滑な事前協議のため、該当の生産緑地の状況について詳しい方がお越しいただくか、事前に土地所有者等に確認の上ご来庁ください。(特に、主たる従事者の死亡・故障を事由とする場合)
| (※2)買取申出の提出書類について |
|---|
買取申出の提出書類は裏面一覧表のとおりとなります。
なお、【1.生産緑地買取申出書】については、事前協議の際にお渡しします。
また、【2.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書】については、主たる従事者の死亡・故障を事由とされる場合に必要となりますが、事前協議の際に買取申出の事由になりうるかを事前確認させていただきますので、事前協議を終えてから羽曳野市農業委員会に証明を願い出てください。
| (※3)都市計画の変更がされるまでの生産緑地について |
|---|
行為制限が解除された場合であっても、都市計画が変更されるまでの間は生産緑地地区内にある土地となります。
一定規模以上の生産緑地地区内の土地を有償譲渡しようとする場合、契約前に別途、【公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出】が必要な場合があります。詳しくは管財用地課までお問い合わせ下さい。
生産緑地地区の指定状況
令和7年12月19日付け(羽曳野市告示第335号)変更について
詳細についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
| 問い合わせ内容 | 羽曳野市役所 (代) 072-958-1111 |
内線 | 所在 |
|---|---|---|---|
| 買取申出について | 都市計画課 | 2572・ 2573 |
本館 |
| 主たる従事者の証明について | 農業委員会事務局 | 4710・ 4711 |
本館 2階 |
| 公有地の拡大の推進に関する法律について | 管財用地課 用地担当 | 2253・ 3790 |
本館 3階 |
| 固定資産税について | 税務課 固定資産税担当 | 1540・ 1541 |
本館 1階 |
| 相続税等の納税猶予について |
お問い合わせは被相続人の住所地を所管する税務署へ。 |
||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
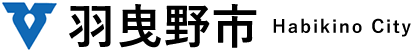


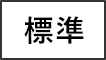
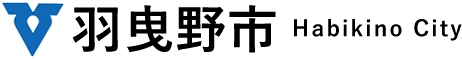

更新日:2025年12月19日