縄文・弥生時代のはびきの
現在わかっている縄文時代の遺跡には、伊賀(いが)遺跡、株山(かぶやま)遺跡、翠鳥園(すいちょうえん)遺跡などがあります。縄文土器や石器が見つかっていて、小さなムラや狩場(かりば)があったと考えられます。伊賀遺跡では、縄文時代の終わり頃の土器棺墓(どきかんぼ)の跡が見つかりました。また株山遺跡では、サヌカイトを材料にした石器製作が行われていたことがわかっています。
弥生時代の遺跡には、喜志(きし)遺跡、駒ヶ谷(こまがたに)遺跡などが存在します。喜志遺跡は、弥生時代中期に栄えた大きなムラの跡で、サヌカイトを使った石器を多量に生産していました。西浦小学校からは、ムラのまつりで使われたと考えられる銅鐸が、穴に埋められた状態で発見されています。
弥生時代後期になると、石川の東の丘陵地帯(きゅうりょうちたい)に駒ケ谷遺跡や御嶺山(ごりょうやま)遺跡などの高地性集落が現れます。見晴らしの良い高い場所にムラが作られた理由は、ムラとムラとの戦いが激しくなり、緊張した社会情勢であったからだと考えられています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
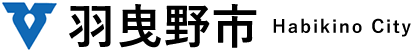


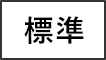
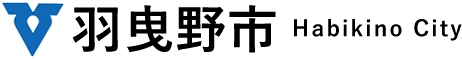
更新日:2024年01月19日